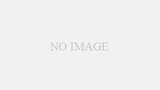パタノール点眼液(一般名:オロパタンジン塩酸塩)は2006年から発売されている点眼液(目薬)です。
アレルギーを抑えるはたらきを持つ「抗アレルギー薬」であり、主に花粉症で生じるような目の充血やかゆみなどに用いられています。
抗アレルギー点眼薬にもいくつかのお薬がありますが、その中でパタノールはどのような特徴のあるお薬で、どのような作用を持っているお薬なのでしょうか。
パタノール点眼液の特徴や効果・副作用について詳しく説明していきます。
1.パタノールの特徴
まずはパタノール点眼液の全体的な特徴について紹介します。
パタノールはヒスタミンのはたらきをブロックすることでアレルギー症状を抑える目薬です。同種の点眼薬と比べてもアレルギーを抑える作用は強めになります。
ヒスタミンはアレルギーを引き起こす原因となる物質(ケミカルメディエーター)の1つです。そのため、このヒスタミンのはたらきをブロックする事ができればアレルギー症状を抑える事が出来ます。
これを狙っているのがパタノールをはじめとした「抗ヒスタミン薬」です。
パタノールは「オロパタジン」という成分が主成分となっていますが、これは「アレロック」という代表的な経口抗ヒスタミン薬にも使われている成分です。
アレロックは花粉症などのアレルギー疾患に処方される飲み薬で、効果の強さに定評があるお薬です。一方で副作用もやや多めで、特に眠気が他の抗ヒスタミン薬よりも多く認められます。
パタノールはアレロックと同様、アレルギーを抑える作用は強めです。かつ、局所(目)にのみ作用し体内にほとんど移行しないため、お薬の成分が全身に回りにくく、眠気などの副作用はほとんど起こしません。
パタノールは主に「抗ヒスタミン作用」によってアレルギー症状を抑えますが、それ以外のケミカルメディエーターや炎症性サイトカインなど多くの物質のはたらきを抑える作用があり、これにより強力にアレルギー症状を抑える事が出来ます。
以上から、パタノール点眼液の特徴として次のようなことが挙げられます。
【パタノール点眼液の特徴】
・眼に生じたアレルギー反応(充血やかゆみなど)を抑える作用を持つ
・ヒスタミンをはじめ、様々なケミカルメディエーター・炎症性サイトカインのはたらきを抑える
・同種の抗アレルギー点眼薬の中でも効果は強い
・局所(目)にしかほとんど作用しないため、副作用が少ない
2.パタノールはどのような疾患に用いるのか
パタノールはどのような疾患に用いられるのでしょうか。添付文書には次のように記載されています。
【効能又は効果】
アレルギー性結膜炎
アレルギー性結膜炎とは、眼の結膜(いわゆる「白目」の部分)にアレルギー反応が生じてしまう状態です。アレルギー反応は炎症反応を引き起こすため、結膜にアレルギーが生じると結膜炎になります。
代表的なケースとしては、花粉症で生じるアレルギー性結膜炎が挙げられます。
花粉症では「花粉」というアレルギー物質(アレルゲン)が結膜に付着する事で、結膜にアレルギー反応が引き起こされます。
パタノールはアレルギー性結膜炎に対して、どのくらい有効なのでしょうか。
パタノールの有効率は91.2%と報告されており、しっかりとした効果がある事が分かります。
臨床的な実感としても、パタノールは抗アレルギー点眼液の中でもしっかりとした効果があり、患者さんからの評価も高いお薬です。
3.パタノールにはどのような作用があるのか
パタノール点眼液はどのような作用機序によって、アレルギー症状を抑えてくれるのでしょうか。
パタノールの作用について詳しく紹介させて頂きます。
Ⅰ.抗ヒスタミン作用
パタノールは抗ヒスタミン薬というお薬に属し、その主な作用は「抗ヒスタミン作用」になります。これはヒスタミンという物質のはたらきをブロックするという作用です。
アレルギー症状を引き起こす物質の1つに「ヒスタミン」があります。
アレルゲン(アレルギーを起こすような物質)に暴露されると、アレルギー反応性細胞(肥満細胞など)からアレルギー誘発物質(ヒスタミンなど)が分泌されます。これが受容体などに結合することで様々なアレルギー症状が発症します。
ちなみに肥満細胞からはヒスタミン以外にもアレルギー誘発物質が分泌されますが、これらはまとめて「ケミカルメディエータ―」と呼ばれています。
パタノールのような抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応性細胞からヒスタミンが分泌されるのを抑える作用があります。またヒスタミンが結合する部位であるヒスタミン受容体をブロックする作用もあります。
これらの作用によりアレルギー症状を和らげてくれます。
Ⅱ.その他のケミカルメディエーター抑制作用
ケミカルメディエーターはヒスタミン以外にもあります。
パタノールはヒスタミン以外にも、トリプターゼ、プロスタグランジンD2などのケミカルメディエーターにも作用します。
トリプターゼ、プロスタグランジンD2も肥満細胞から分泌され、身体にアレルギー反応を引き起こす物質になります。
パタノールはこれらのケミカルメディエーターの分泌を抑えるはたらきもあり、これによってもアレルギー症状を緩和させてくれます。
Ⅲ.抗炎症作用
アレルギー反応が起こると、その部位には炎症が生じます。
炎症は、
- 発赤(赤くなる)
- 腫脹(腫れる)
- 熱感(熱くなる)
- 疼痛(痛くなる)
の4つの徴候を生じる状態のことで、感染したり受傷したりすることで生じます。またアレルギーで生じることもあります。
みなさんも身体をぶつけたり、ばい菌に感染したりして、身体がこのような状態になったことがあると思います。これが炎症です。
眼に炎症が生じれば、眼が赤くなり、腫れ、熱を持ち、痛みを感じるようになります。
パタノールはアレルギー反応を抑えるだけでなく、このような炎症反応を緩和するはたらきもあります。
具体的には炎症性サイトカイン(炎症を引き起こす物質)であるインターロイキン6(IL-6)・インターロイキン8(IL-8)が結膜上皮細胞から産生・分泌されるのを抑えるはたらきがあります。
またTNFαという炎症性サイトカインが肥満細胞から分泌されるのを抑制するはたらきもあります。
4.パタノールの副作用
パタノールにはどんな副作用があるのでしょうか。また副作用の頻度はどのくらいなのでしょうか。
パタノールの副作用は0.6%と報告されています。眼局所にしか作用しないお薬ですので、副作用は多くはありません。
生じうる副作用としては、
- 眼の刺激感
- 眼痛
- 眼瞼炎
- 眼瞼浮腫
- 眼のそう痒
とほとんどが眼局所の副作用になります。
また眼の症状以外としては、
- 頭痛
- ALT上昇
などの報告がありますが、頻度は極めてまれです。
パタノールは重篤な副作用の報告もほとんどなく、基本的には安全に使用できるお薬です。
5.パタノールの用法・用量と剤形
パタノールは、
パタノール点眼液0.1% 5ml
の1剤形のみがあります。
パタノールの使い方としては、
通常、1回1〜2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼する。
となっています。
実際は厳密に1日4回を点眼する必要はなく、ある程度柔軟に考えて頂いて問題ありません。
6.パタノールはコンタクトレンズの上から点眼できるのか
点眼液を処方すると、患者さんから良く聞かれる質問があります。
それは「コンタクトを付けたまま点眼して大丈夫ですか?」というものです。
この回答は、
- 「ハードコンタクトレンズは大丈夫」
- 「ソフトコンタクトレンズはパタノールを点眼して10分以上待ってからコンタクトレンズを装着する事」
というのが答えになります。
パタノール点眼液にはベンザルコニウム塩化物という防腐剤が含まれています。ベンザルコニウム塩化物はコンタクトレンズに吸着されてしまうことが知られており、これによってソフトコンタクトレンズを変形させてしまう事があります。
そのためソフトコンタクトレンズ装着時にパタノールを点眼する事はあまり推奨されません。
ただしパタノールを点眼してから10分程度待ってソフトコンタクトレンズを装着すれば、ベンザルコニウム塩化物はほとんど吸着されないという報告がありますので、どうしてもパタノール点眼液も使いたいし、コンタクトレンズもつけたいという場合は、このように点眼後に少し待ってからコンタクトを装着するようにすると良いでしょう。
7.パタノールが向いている人は?
以上から考えて、パタノールが向いている人はどんな人なのかを考えてみましょう。
パタノールの特徴をおさらいすると、
・眼に生じたアレルギー反応(充血やかゆみなど)を抑える作用を持つ
・ヒスタミンをはじめ、様々なケミカルメディエーター・炎症性サイトカインのはたらきを抑える
・同種の抗アレルギー点眼薬の中でも効果は強い
・局所(目)にしかほとんど作用しないため、副作用が少ない
といったものがありました。
パタノールはアレルギー症状を抑える目薬で、作用も強いため、患者さんからも人気のある抗アレルギー点眼薬の1つです。
眼のみに作用し、体内にほとんど吸収されないため、効果が強い割に副作用が少なく、使い勝手の良いお薬になります。
そのため、アレルギー症状が目だけにとどまっている方には良い適応になります。
反対にアレルギー症状が目だけではなく、鼻水も出たりと症状が多岐に渡る場合は、飲み薬を服用するなどして、全身にお薬が効くようにした方が良いでしょう。